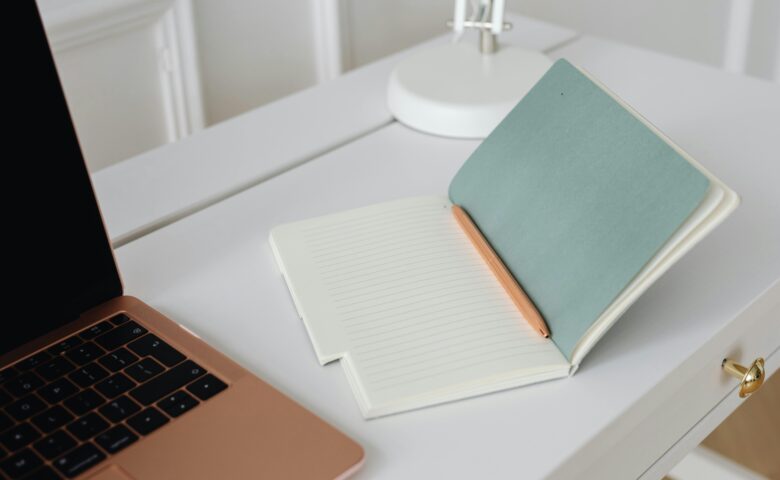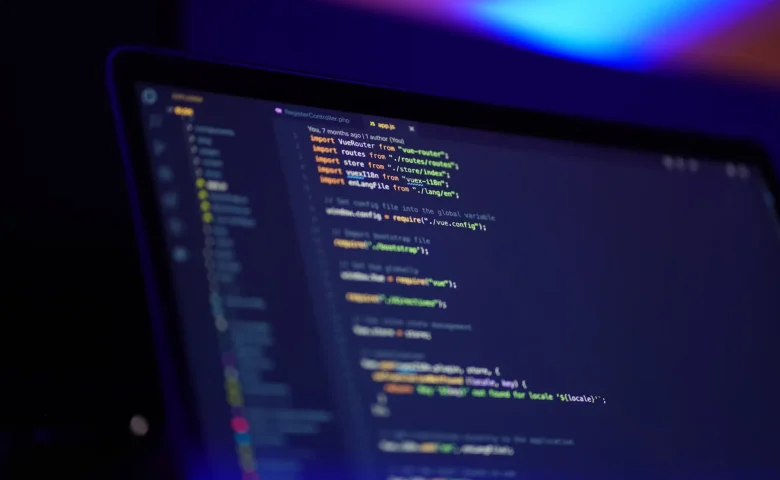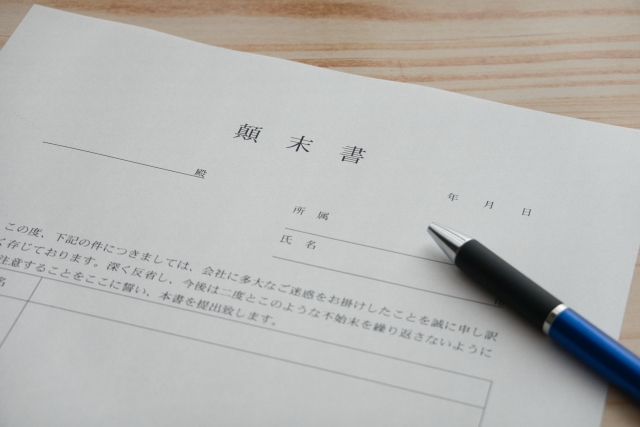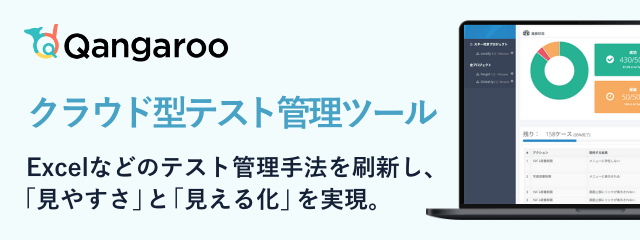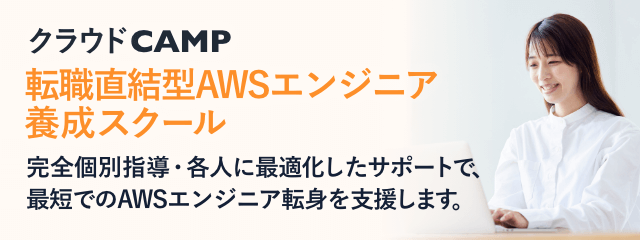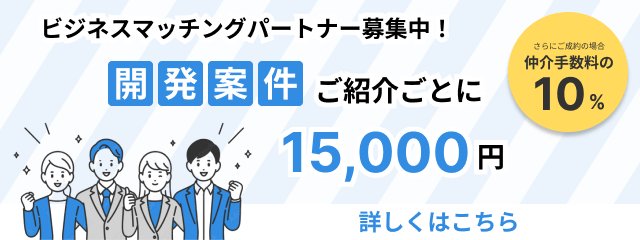2023.10.25
サーバー構築とは?基礎から応用、目的別のサーバー選びと実践的構築手順

システムを動かすにはサーバーが必要です。しかし、サーバーには複数の種類があるため、どのサーバーが適切かお悩みではないでしょうか。
実は、適切ではないサーバーを選んでしまうと、システムの価値は一気に下がってしまうでしょう。なぜならサーバーには、種類によって向いているシステムがあるからです。そこで本記事では、サーバーの基礎知識を深めつつ、目的にあったサーバーについて解説します。
この記事でわかること
- サーバーについて
- サーバーの種類と適したシステム
- サーバー構築を行う際のポイント
目次
サーバー構築の基礎知識

サーバー構築とは、Webシステムなどを提供する際の土台となるサーバー環境を作ることです。サーバーはシステムやサービスごとに異なるため、複数のシステムやサービスがある場合は、一つひとつ構築していく必要があります。
この章では、サーバー構築について理解を深めるために、はじめにサーバーの基礎知識を解説します。
サーバーとは
サーバーとは、情報が保存されている保管庫です。ネットワークを介して、情報やサービスを別のコンピューターに提供します。ひとくちに「情報」といってもさまざまで、具体例を挙げると以下のとおりです。
- 顧客情報
- 社内資料
- 売り上げ
- 購入情報
- レイアウト情報
ユーザーは、これらをサーバーに対してリクエストすることで、サーバーから提供される情報を受け取れます。
ハードウェアとしてのサーバー・ソフトウェアとしてのサーバー
サーバーという名称は、ハードウェアに対してもソフトウェアに対しても用いられます。ハードウェアとしてのサーバーは、それ自体をサーバーとして扱うコンピューターのことです。サーバーコンピューターやサーバーマシンと呼ばれます。
一方、ソフトウェアとしてのサーバーは、サーバー機能を提供しているソフトウェアのことです。サーバーソフトやサーバーウェアと呼ばれます。区別したい場合は、それぞれサーバーコンピューター、サーバーウェアと呼ぶと伝わりやすいでしょう。
ハードウェアとしてのサーバーの種類
ハードウェアとしてのサーバーには、以下のような種類があります。
- 共用サーバー
- 専用サーバー
- クラウドサーバー
- VPS
この章では、一つひとつ詳しく解説します。
共用サーバー
ひとつのサーバーを複数人で共有して使います。ユーザーは、サーバー貸出業者からサーバーをレンタルしている状態です。そのため、レンタルサーバーとも呼ばれます。
共用サーバーのメリットは、以下のとおりです。
- 価格が安い
- 簡単に使い始められる
- 専門的な知識がほとんどいらない
- メンテナンスはサーバーの運営会社が行ってくれる
一方、デメリットには以下の内容が挙げられます。
- サーバーの運営会社に依存してしまう
- 共有しているほかのユーザーの悪影響を受けやすい
- サーバーの管理権がないため、好きなアプリケーションをインストールできない
サーバーを用意するスキルや知識はないものの、高パフォーマンスのサーバーが欲しい方におすすめです。
専用サーバー
専用サーバーは、物理サーバーを1台丸ごと専有して使えます。メリットは以下のとおりです。
- ほかのユーザーの影響を受けない
- サーバーの管理権が付与されるので、好きなOSを選べたり、好きなアプリケーションをインストールできたりする
一方、デメリットは以下のとおりです。
- メンテナンスのためのスキルや知識が必要
- 専有できるうえに、ハイスペックなので価格が高い
サーバー管理に関する知識があり、サーバーを自由にカスタマイズしたい方におすすめです。
クラウドサーバー
クラウドサーバーは、ユーザーそれぞれに仮想のサーバーが提供される仕組みです。仮想サーバーは物理サーバーの上に存在し、ユーザーはネットワーク経由で仮想サーバーにアクセスします。なお、メリットは以下のとおりです。
- ユーザー一人ひとりが仮想サーバーを持っているため、ほかのユーザーの影響を受けない
- 仮想サーバーにはユーザーごとに管理権が与えられるため、アプリケーションを自由にインストールできる
- 使用料は、1日ごと、1時間ごとで区切られるため、工夫次第では料金を抑えられる
一方で、以下のようなデメリットもあります。
- サーバー運営会社に依存してしまう
- 時間単価なので、長期的に利用するとコストが高くなることもある
高コストを投じる余裕があり、自由度の高いサーバーを用意してもらいたい方におすすめです。
VPS
VPSとは、仮想専用サーバーの略称です。クラウドサーバーのように物理サーバーの上に仮想サーバーが存在します。その仮想サーバーを、ユーザー一人ひとりに提供し、ユーザーは提供された仮想サーバーを専有して使えるという仕組みです。
メリットとしては以下が挙げられます。
- 仮想サーバーの管理権を持っているので、自由にカスタマイズできる
- レンタルサーバーよりもほかのユーザーの影響を受けなくなる
一方でデメリットは以下のとおりです。
- クラウドサーバーほど拡張性がない
- サーバーを自分で構築、メンテナンスするスキルが必要になる
高パフォーマンスは求めておらず、コストを抑えたい方におすすめです。
ソフトウェアとしてのサーバーの種類

ソフトウェアとしてのサーバーの種類には、以下の7種類があります。
- データベースサーバー
- Web サーバー
- アプリケーションサーバー
- ファイルサーバー
- メールサーバー
- DNSサーバー
- FTPサーバー
データベースサーバー
データベースが搭載されているサーバーです。ユーザーからの要求がくると、データベース内にある適切な情報をユーザーへ提供します。
たとえば、賃貸サイトにアクセスし、家賃6万円以下でオートロックつきの物件を探すとします。このとき、データベースサーバーは、条件に合った賃貸のデータをデータベースのなかから探して、ユーザーに提供しています。なお、これらの情報を管理しているのは、データベース管理システムです。
Web サーバー
ユーザーにWebサイトやブログといったWebページを表示するサーバーです。したがって、Webページを構成している情報が保存されています。
たとえば、テキストが記載されたHTMLファイルやページのレイアウトが記載されているCSSファイル、画像、動画などです。ブログやWebサイトを運営する際、Webサーバーは必要不可欠となります。
アプリケーションサーバー
Webシステムに搭載されたアプリケーションの機能を動かすためのサーバーです。
Webサーバーからのリクエストに応じて、JavaScriptやPHP、Rubyなどのプログラムを実行し、必要なデータを取り出します。取り出したデータは、Webサーバーに送り返します。簡潔に説明すると、プログラミング言語で作られたアプリを動かして、動的コンテンツを作成するサーバーということです。
ファイルサーバー
ファイル共有機能に特化したサーバーです。同じネットワークに接続している人同士でデータを共有、使用します。なお、ファイルサーバーには以下の2種類があります。
- オンプレミス型:自社にサーバーを設置して管理、運用する
- クラウド型:クラウドサービス上にサーバーを設置する
昨今、注目を集めているのは、クラウド型ファイルサーバーです。
メールサーバー
メールを送受信するときに使われるサーバーです。厳密には、送信用と受信用でわかれています。送信サーバーはSMTPサーバー、受信サーバーはPOPサーバーやIMAPサーバーと呼ばれるのが一般的です。
メール送信を行う際、SMTPサーバーはDNSサーバーとともに宛先を探し送信します。DNSサーバーは次の節で解説しています。
また、POPサーバーではメールの保管、IMAPサーバーではメールの受信を行います。なお、メールの送受信を行うには、メールサーバーからの承認を得なければいけません。
DNSサーバー
DNSサーバーでは、IPアドレスとドメインが結びつけられます。IPアドレスとは、Web上の媒体の識別番号、現実世界の住所のようなものです。ドメインとは、IPアドレスに名前をつけたもので、Webサイトの名前として扱われます。
DNSサーバーは、IPアドレスをドメインに変換する役割を果たしています。インターネットを利用するうえで欠かせないサーバーです。
FTPサーバー
FTPサーバーは、Webサーバーにファイルを送受信するために用いられるサーバーです。Webサイトを作成するときは、Webサーバーにファイルをアップロードします。その際、ファイルをアップロードするために、用いられるのがFTPサーバーです。
Webサーバーは、ユーザーの要求に応じてファイルを提供するだけです。一方でFTPサーバーの場合、ユーザーはFTPサーバーにファイルをアップロードしたり、反対にFTPサーバーからデータをダウンロードしたりできます。
サーバー構築において重要なポイント
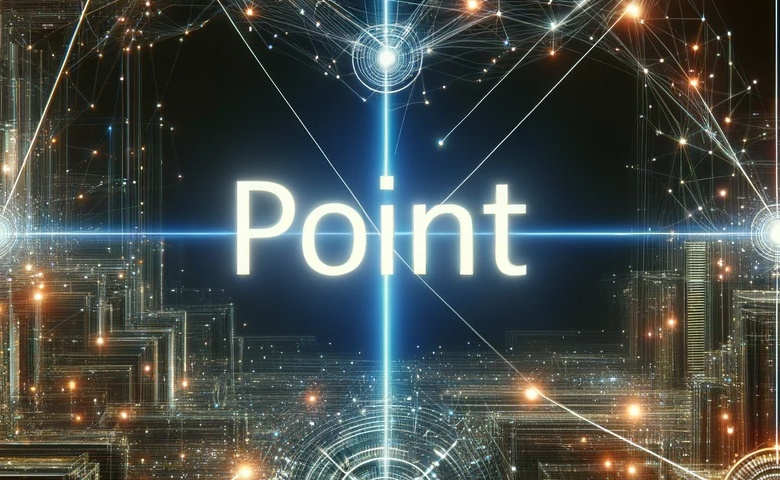
サーバー構築において重要なポイントは以下の2点です。
- 自社での構築の場合
- 外部委託する場合
自社での構築の場合
自社でサーバーを構築する場合、運用にどのくらいの費用がかかるか把握しておくことが重要です。サーバー構築には、初期費用や運用費用などの高い費用がかかります。加えて、サーバーを設置する場所、人材、設備も必要です。これらのコストをもとに、自社でサーバー構築を行うべきか検討しましょう。
また、実際に自社でサーバーを構築する場合は、目的を明確にしてください。理由は、目的によって最適なサーバーが異なるからです。たとえば、ECサイトのような多くのユーザーの利用が予想されるサイトを運営する場合は、VPSのような高負荷にも耐えられるサーバーが適切です。
外部委託する場合
外部委託する場合も、自社で構築する場合と同様に、サーバー構築を行う目的を明確にしましょう。本記事で紹介したとおり、サーバーには専用サーバーや共用サーバー、VPSといったさまざまなサーバーが存在します。それぞれに長所と短所があるため、できるだけ長所を活かせるようなサーバー選びが重要です。
長所を活かすためには、サーバーを構築したい理由を明確にし、共有する必要があります。たとえば、知識がなくても運用しやすいサーバーが欲しい場合、後々になって専門知識が必要になる専用サーバーは選ぶべきではありません。共用サーバーのような、知識がなくても使えるサーバーが望ましいです。
サーバー構築を含めたITインフラ構築は、ぜひテクノデジタルのエンジニアチームにお任せください。こちらのページでは、当社のITインフラ構築の強みを紹介しています。
まとめ

サーバーとは、情報が保存されている保管庫です。ネットワークを介して、情報やサービスをほかのコンピューターに提供するという仕組みです。
また、サーバーにはハードウェアとしてのサーバーとソフトウェアとしてのサーバーが存在します。そのため、適切なサーバーを選ぶためには、サーバー構築を行う目的を明確にすることが重要です。
もし、サーバー選びにお悩みの方は、テクノデジタルまでお問い合わせください。サーバーに関する経験が豊富なスタッフが、ヒアリングから構築まで丁寧にサポートいたします。
投稿者
-
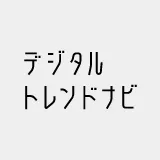
システム開発、Webサイト制作、ECサイトの構築・運用、デジタルトランスフォーメーション(DX)など、デジタルビジネスに関わる多岐の領域において、最新のトレンド情報や実践的なノウハウを発信してまいります。
こんな記事が読まれています
まだデータがありません。
同じカテゴリの記事
新着記事
人気の記事
まだデータがありません。