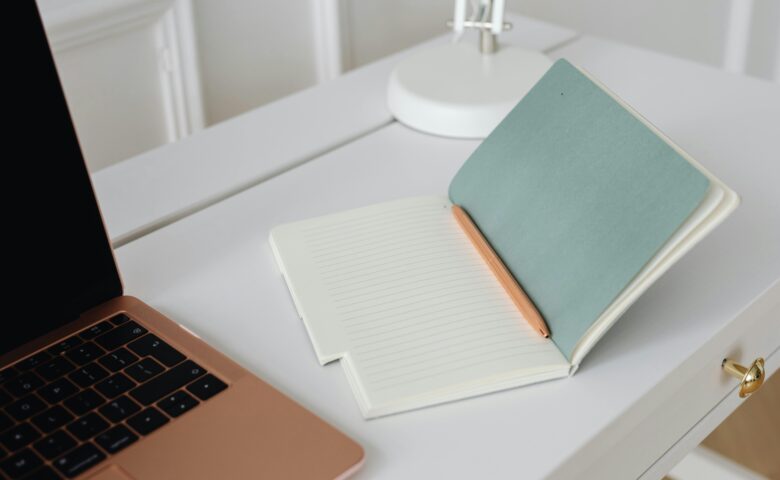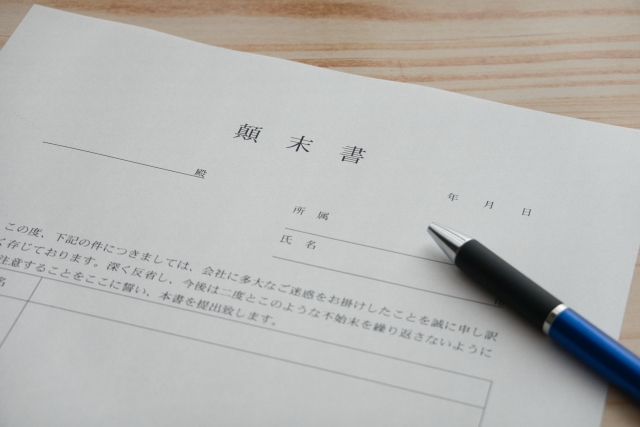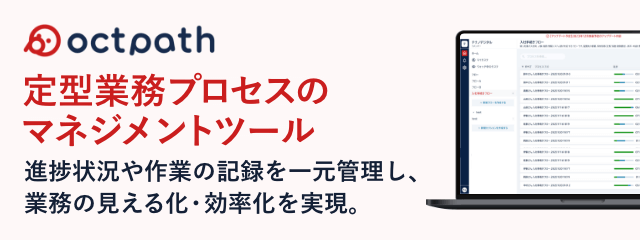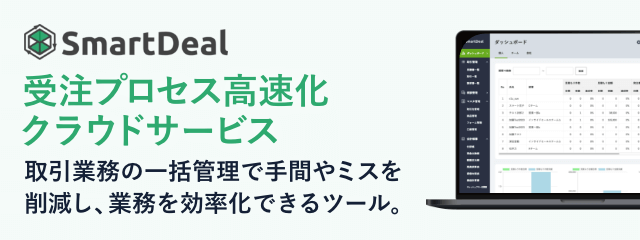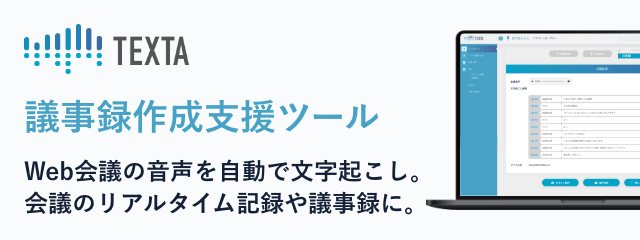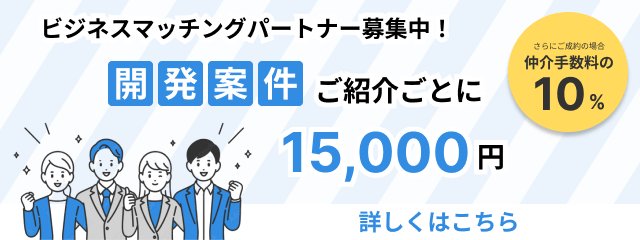2025.08.21
なぜ「認識の齟齬」がプロジェクトを頓挫させるのか

「認識の齟齬」とは、複数の人が物事に対して持つ理解や解釈にずれや食い違いが生じている状態を指します。
デジタルトランスフォーメーション(DX)は、現代ビジネスにおいて企業が競争力を維持・向上させるための不可欠な戦略です。しかし、多くの企業がDXの推進に乗り出す中で、「認識の齟齬」が、プロジェクトの大きな障害となるケースが後を絶ちません。
本記事では、DX推進における「認識の齟齬」がなぜ発生するのか、その具体的な課題や失敗事例を挙げながら深掘りし、どのようにすればこの見えない壁を乗り越え、DXを成功に導くことができるのか、具体的な解決策を提示します。
目次
「認識の齟齬」が生まれる背景

DX推進において「認識の齟齬」が生じる原因は多岐にわたりますが、主に以下のような要因が挙げられます。
経営層と現場のDX理解度のギャップ
DXは単なるITツールの導入ではなく、ビジネスモデルや企業文化そのものの変革を伴います。
しかし、経営層がDXの本質的な意味や長期的なビジョンを十分に理解せず、単なるITコスト削減や業務効率化と捉えている場合があります。一方で、現場は日々の業務に追われ、DXの必要性を感じていなかったり、新しいシステムへの適応に抵抗を感じたりすることもあります。
このように、DXの目的や価値に対する認識のずれが、プロジェクトの方向性を曖昧にし、推進の足並みを乱す最大の原因となります。
部門間の連携不足と目的意識の不一致
DXは特定の部門だけで完結するものではなく、全社横断的な取り組みが求められます。しかし、DX推進部門が「全体最適」を目指す一方で、事業部門が「目の前の作業支援」を優先するなど、それぞれの部署が異なる目的意識を持っていると、協力体制が築きにくくなります。
情報システム部門、営業部門、製造部門など、それぞれの立場や役割からくる利害の対立や優先順位の違いが、プロジェクトの進行を停滞させます。特に、人間関係における課題も指摘されており、部門間のコミュニケーション不足が認識の齟齬をさらに深める悪循環に陥ることがあります。
DX推進におけるビジョン・目標の不明確さ
「何のためにDXを進めるのか」「DXによってどのような状態を目指すのか」という明確なビジョンや具体的な目標が設定されていない場合、関係者それぞれの解釈でプロジェクトが進んでしまい、結果として期待した成果が得られないことがあります。
特に、ベンダー企業との協業においても、自社の求める要件や目指す姿が不明確だと、提供されるシステムやツールとの間で認識のずれが生じ、手戻りや期待外れの結果につながる可能性があります。
ITリテラシーのばらつきとデジタルデバイド
社内の従業員のITリテラシーに大きなばらつきがあることも、認識の齟齬を生む一因です。新しいデジタル技術への理解不足や不安から、変化を拒む従業員がいる場合、DX推進は停滞します。特定の従業員にIT知識が偏り、情報格差(デジタルデバイド)が生じることで、共通の理解に基づいた議論が難しくなります。
コミュニケーションチャネルの不足と質の問題
リモートワークの普及など働き方の変化により、対面でのコミュニケーション機会が減少し、情報共有が不足しがちです。テキストベースのコミュニケーションでは伝わりにくいニュアンスや背景が理解されず、誤解が生じることも少なくありません。
また、形式的な情報共有にとどまり、従業員の疑問や不安に寄り添った双方向性のコミュニケーションが不足している場合も、認識の齟齬が解消されにくくなります。
「認識の齟齬」が引き起こすDX失敗の具体例

「認識の齟齬」は、DXプロジェクトの様々な段階で失敗を引き起こす可能性があります。
| 戦略策定段階での失敗 | 経営層が「DXは最新システムの導入」と捉え、現場の業務プロセスや課題を無視した大規模なシステム刷新を決定。結果として現場からの強い反発を受け、導入が進まない、あるいは導入されても活用されず「使われないシステム」となる。 |
|---|---|
| 開発・導入段階での失敗 | 事業部門が「業務効率化」を優先する一方で、DX推進部門が「データ活用による新規事業創出」を目指し、システム要件の認識が一致しないまま開発が進行。完成したシステムが事業部門のニーズと乖離しており、結局ほとんど使われずに投資が無駄になる。 |
| 運用・定着段階での失敗 | 新しいツールやシステムを導入したものの、従業員への十分なトレーニングやサポートがなく、デジタルリテラシーの低い従業員が使いこなせない。あるいは、新しい働き方や文化への変革が伴わず、これまでのやり方に固執してしまうため、デジタル化の効果が限定的となる。 |
これらの失敗事例の根底には、いずれも関係者間の「認識の齟齬」が存在します。明確なビジョン、共通の目標、そして効果的なコミュニケーションが欠如しているために、プロジェクトが空中分解してしまうのです。
「認識の齟齬」を解消し、DXを成功に導くための解決策

DX推進における「認識の齟齬」を解消し、プロジェクトを成功に導くためには、戦略的かつ継続的なアプローチが不可欠です。
①DXの目的とビジョンの明確化・共有
最も重要なのは、経営層がDXの目的とビジョンを明確にし、それを全社に徹底的に共有することです。「なぜDXが必要なのか」「DXを通じてどのような未来を目指すのか」を具体的な言葉で語り、従業員一人ひとりが「自分ごと」として捉えられるように繰り返し発信します。
- 多層的かつ継続的なコミュニケーションの設計
部門間、階層間での密なコミュニケーションを促進するための仕組みを構築します。 - 定期的な全体説明会やワークショップの開催
DXの進捗状況や成果を可視化し、従業員からの疑問や不安に直接答える場を設けます。 - 部門横断型プロジェクトチームの設置
異なる部門のメンバーが協力し、多様な視点を取り入れながら共通の目標に向かうことで、自然と認識合わせが促進されます。 - デジタルコミュニケーションツールの活用
社内SNSやチャットツールを導入し、気軽に情報共有や意見交換ができる環境を整備します。ただし、ツールの導入だけでなく、その活用を促すためのガイドラインや文化醸成も重要です。 - 現場の声の吸い上げ
経営層やDX推進部門が積極的に現場の意見に耳を傾け、実情に即した戦略を立てることで、現場の納得感を高め、抵抗感を軽減します。
②DX人材の育成とITリテラシーの底上げ
社内全体のデジタルリテラシーを向上させるための教育プログラムを継続的に実施します。
- 研修・勉強会の実施
デジタル技術の基礎知識から、DX推進における具体的な活用事例まで、従業員のレベルに合わせた研修を提供します。 - DX推進を担う人材の育成
専門的な知識を持つDX人材を育成・確保することで、社内のDXを加速させるとともに、各部門の「ハブ」となり、認識合わせを促進する役割を担ってもらいます。 - スモールスタートと成功事例の共有
一度に大規模な変革を行うのではなく、小規模なプロジェクトから開始し、成功事例を積極的に社内で共有することで、成功体験を積み重ね、DXへの期待感と理解を醸成します。 - 計画の見直しと改善
DXは長期的な取り組みであるため、途中で市場環境や社内外の状況が変化することは往々にしてあります。定期的に計画を見直し、必要に応じて軌道修正を行うことで、認識のずれが拡大するのを防ぎます。 - 外部パートナーとの関係構築と要件定義の徹底
ベンダー企業などの外部パートナーと協力する場合、要件定義の段階で徹底的に認識合わせを行います。 - 定期的な進捗確認とフィードバック
開発プロセスにおいて定期的に進捗を確認し、課題や認識のずれが生じていないかを早期に検出し、迅速に修正する体制を構築します。 -
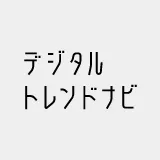
システム開発、Webサイト制作、ECサイトの構築・運用、デジタルトランスフォーメーション(DX)など、デジタルビジネスに関わる多岐の領域において、最新のトレンド情報や実践的なノウハウを発信してまいります。
まとめ

DX推進において「認識の齟齬」は、避けられない課題でありながら、その重要性が見過ごされがちです。しかし、この見えない壁を放置することは、プロジェクトの失敗、ひいては企業の競争力低下に直結します。
DXを成功させるためには、経営層から現場まで、すべての関係者が「なぜDXが必要なのか」「DXで何を目指すのか」という共通の認識を持つことが不可欠です。そのためには、明確なビジョンの共有、多層的で継続的なコミュニケーション、従業員のITリテラシー向上、そして柔軟なプロジェクト推進が求められます。
「認識の齟齬」とは、複数の人が物事に対して持つ理解や解釈にずれや食い違いが生じている状態を指します。なぜ発生しプロジェクトを頓挫させるのか?具体的な原因、失敗例、そして成功に導くための解決策を解説。
投稿者
こんな記事が読まれています
まだデータがありません。