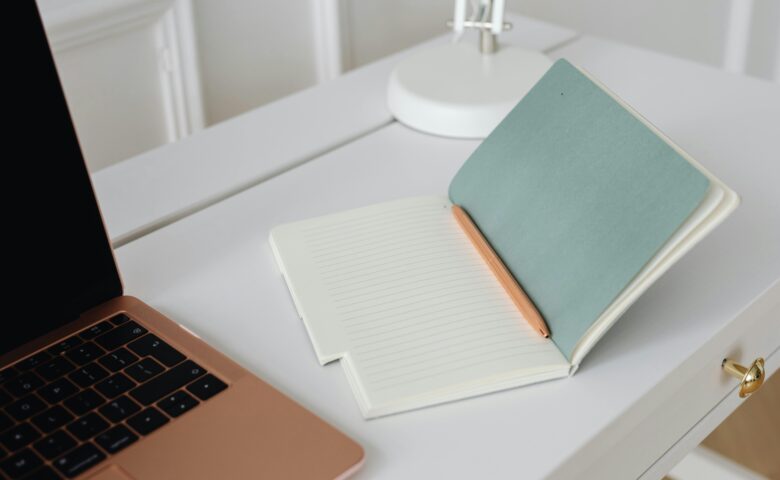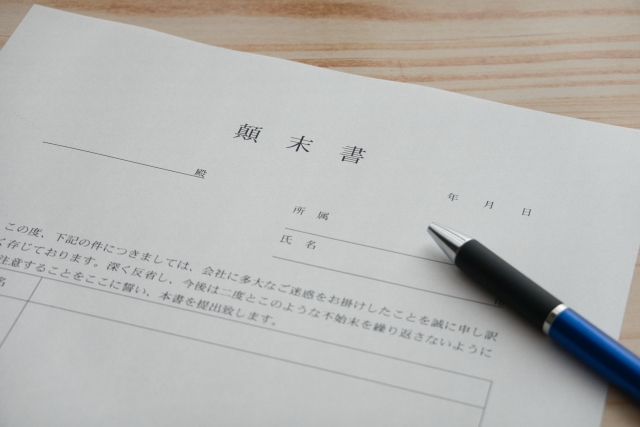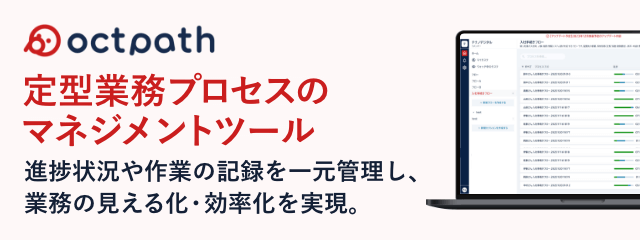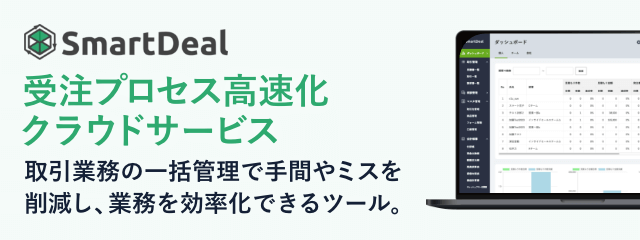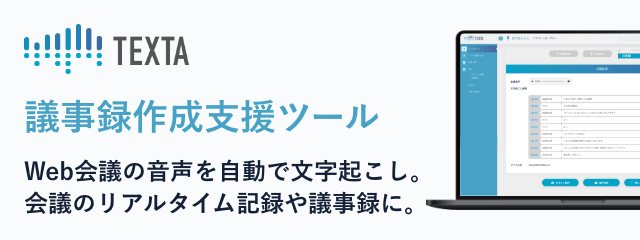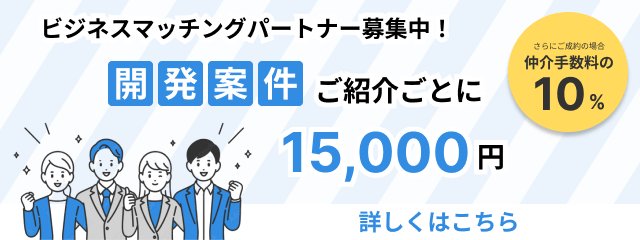2025.05.13
引継ぎとは?メリットや引継書の作成方法もわかりやすく解説

引継ぎとは、前任者が行っていた業務内容や進め方、注意点などを後任者に伝える重要なプロセスです。適切な引継ぎが行われないと、業務の停滞やミスの発生につながるリスクがあります。
本記事では、引継ぎの基本やメリット、具体的な進め方、引継ぎ書の作成方法について詳しく解説します。円滑な引継ぎを行い、業務の継続性と生産性を維持するための参考にしてください。
目次
引継ぎとは?

引継ぎとは、前任者が担当していた業務内容、手順、取引先情報などを後任者に伝達し、業務がスムーズに進むようにするプロセスです。単なる業務手順の説明にとどまらず、実務上のポイントや関係者とのコミュニケーション方法も共有する必要があります。
業務の引継ぎにはフロー図を使った管理ツール「octpath」がおすすめです。
引継ぎが必要になるシーン
引継ぎが必要になるのは、以下のような状況です。
- 異動や退職に伴う担当者の交代
- 長期休暇や産休・育休の取得
- プロジェクトの担当者変更
いずれのケースでも、引継ぎが不十分だと業務の停滞や混乱が発生するリスクがあります。
引継ぎをしないと発生するリスク
引継ぎが行われない場合、以下のような問題が起こる可能性があります。
- 業務の手順が分からず、作業の遅延が発生
- 顧客対応の不備やクレームの増加
- 情報の紛失やデータの引継ぎ漏れ
こうしたリスクを回避するためには、計画的かつ丁寧な引継ぎが欠かせません。
引継ぎを行う3つのメリット

続いては、引継ぎを行うメリットを3つご紹介します。
1. 仕事全体の生産性が落ちない
引継ぎがしっかりと行われると、後任者が業務の全体像を正確に理解できるため、無駄な確認や調整に時間を取られずに済みます。さらに、業務の目的や優先順位を共有することで、後任者は自ら判断しやすくなり、スムーズに業務を進められます。業務の停滞が防がれ、チームや組織全体の生産性を維持することができます。
2. 企業の信頼が維持できる
引継ぎが不十分だと、顧客からの問い合わせ対応が遅れたり、重要な情報が伝わらなかったりするリスクがあります。適切な引継ぎを行うことで、こうしたトラブルを防ぎ、顧客対応の品質が維持されます。 また、後任者が自信を持って業務に取り組めることで、取引先や関係者の信頼を損なうリスクを軽減できます。結果として、企業の信頼性や評価の維持につながります。
3. 前任者の負担を軽減できる
引継ぎが不十分だと、前任者は退職や異動後も頻繁に連絡を受け、対応に追われることがあります。しっかりとした引継ぎを行い、資料やマニュアルを整えておくことで、後任者は自立して業務に取り組めるようになります。その結果、前任者が後任者のフォローに時間を取られることが減り、安心して次のステップに進むことができます。
引継ぎ方法

ここからは引継ぎの具体的な方法をご紹介します。気を付けるポイントも記載しているのでぜひ参考にしてください。
業務の引継ぎにはフロー図を使った管理ツール「octpath」がおすすめです。 15日間の無料トライアルで操作をお試しください!
①事前準備をする
引継ぎの準備段階では、まず担当業務の全体像を把握し、業務の流れや関係者をリストアップすることが重要です。具体的には、以下の情報を整理するとスムーズに進められます。
- 日常的な業務とイレギュラー対応
- 取引先や関係者の連絡先
- 使用しているシステムやツールの情報
- 注意点や過去のトラブル事例
②資料の作成をする
引継ぎ資料は、後任者が独力で業務を進める際のガイドとなるため、できるだけ具体的かつ実践的に作成するのがポイントです。業務の手順や流れを時系列で整理し、必要な書類やデータの場所、業務の優先順位なども明記しておきましょう。 また、チェックリスト形式にすることで、抜け漏れを防ぎやすくなります。資料には業務の背景や目的も記載すると、後任者の理解がより深まります。万が一の際の「トラブル時の対応方法」や「確認すべき担当者」なども盛り込むと、後任者が安心して業務に取り組めるでしょう。
③後任者への引継ぎを行う
資料を基に、後任者に業務の進め方を具体的に説明します。重要なのは、口頭の説明だけでなく、実際の作業手順を実演しながら伝えることです。
例えば、システム操作や資料の管理方法などは、後任者が実際に操作する場面を見せることで理解が深まります。質問の時間を設け、後任者が不安に感じる点を確認しながら進めると、より効果的な引継ぎが可能です。 引継ぎ当日は、後任者の理解度に応じてペースを調整し、納得するまで丁寧に説明することが大切です。
④後任者に業務を一通りやってもらう
引継ぎの理解度を確認するために、後任者に実際に業務を行ってもらいましょう。前任者が立ち会い、問題点がないか確認するのが理想的です。後任者がミスをした場合は、すぐにフィードバックを行い、適切な対応方法を伝えることで、後任者の不安を解消できます。
また、手順の不明点や資料の不足に気づいた場合は、その都度修正を加えると、より精度の高い引継ぎが実現できます。さらに、後任者に「どの場面で迷ったのか」や「理解しにくかった点」を確認し、資料の補足や業務フローの改善を行うことで、引継ぎの質が向上します。
⑤後任者のフォローをする
引継ぎ完了後も、一定期間は後任者のサポートを行いましょう。具体的には、業務に関する質問を随時受け付けたり、進捗を確認する時間を設けたりすることで、後任者が自信を持って業務に取り組めるようになります。
特に、繁忙期や重要なプロジェクトの対応などは、想定外の問題が発生しやすいため、前任者がサポート役として関与することで、業務の安定が図れます。また、関係者や他部署に「後任者の対応状況」を伝えておくことで、後任者が安心して業務を遂行しやすくなります。
引継ぎを行う際のポイント

引継ぎを行う際のポイントをご紹介します!引継ぎ対応をする際には以下のポイントを意識しましょう。
- 余裕を持って引継ぎを行う
- 口頭のみで済ませないようにする
- 後任者に業務の全体像や目的を伝える
- 前任者が経験したトラブルを伝える
- 後任者が理解できるように伝え方を工夫する
- 第三者にも引継ぎをしていることを伝える
業務の引継ぎにはフロー図を使った管理ツール「octpath」がおすすめです。 15日間の無料トライアルで操作をお試しください!
引継ぎ書の作成方法

最後に引継ぎ書の作成方法をご紹介します。ぜひ参考にしてください。
| ①業務内容を洗い出す | 業務内容を洗い出す際は、普段のルーチン業務だけでなく、突発的に発生するイレギュラー対応や、関係部署との調整業務まで網羅することが重要です。 特に業務の流れや関係者、使用しているツール、データの管理場所などは細かくリスト化し、抜け漏れがないようにしましょう。 |
|---|---|
| ②作成スケジュールを設定 | 引継ぎ書の作成には時間がかかるため、計画的に進めることが大切です。無理のないスケジュールを立て、まずは全体のアウトラインを作成したうえで、優先度の高い業務から具体的な内容を書き出すと効率的です。 |
| ③引継ぎ書を作成 | 引継ぎ書には、以下の要素を盛り込むと、分かりやすく実用的な内容になります。 ・業務の目的や重要性 ・業務フローと具体的な手順 ・関係者の役割と連絡先 ・注意点や過去のトラブル事例 ・使用ツールやシステムのログイン情報 これらを時系列やカテゴリ別に整理することで、後任者が迷わずに対応できる引継ぎ書になります。 |
| ④フィードバック | 作成した引継ぎ書は、必ず上司や同僚に確認してもらい、内容の漏れや不明点がないかチェックしましょう。第三者の視点から指摘をもらうことで、より実践的で充実した引継ぎ書に仕上げられます。 |
| ⑤後任者へ引継ぎ | 完成した引継ぎ書を基に、後任者に具体的な業務内容を伝えましょう。実際の作業を一緒に行いながら説明すると、後任者の理解が深まります。 |
業務の引継ぎにはフロー図を使った管理ツール「octpath」がおすすめです。 15日間の無料トライアルで操作をお試しください!
まとめ

引継ぎは、業務の継続性や生産性を維持するために欠かせない重要なプロセスです。適切な引継ぎを行うことで、後任者がスムーズに業務に対応でき、組織全体の信頼性も保たれます。引継ぎの際は、計画的な準備と丁寧な資料作成を意識し、円滑な引継ぎを目指しましょう。
業務の引継ぎにはフロー図を使った管理ツール「octpath」がおすすめです。 15日間の無料トライアルで操作をお試しください!
投稿者
-
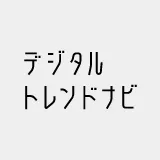
システム開発、Webサイト制作、ECサイトの構築・運用、デジタルトランスフォーメーション(DX)など、デジタルビジネスに関わる多岐の領域において、最新のトレンド情報や実践的なノウハウを発信してまいります。
こんな記事が読まれています
まだデータがありません。