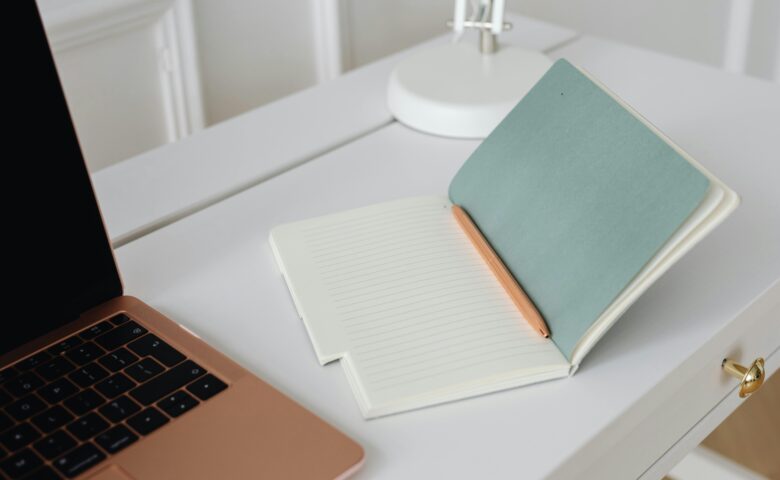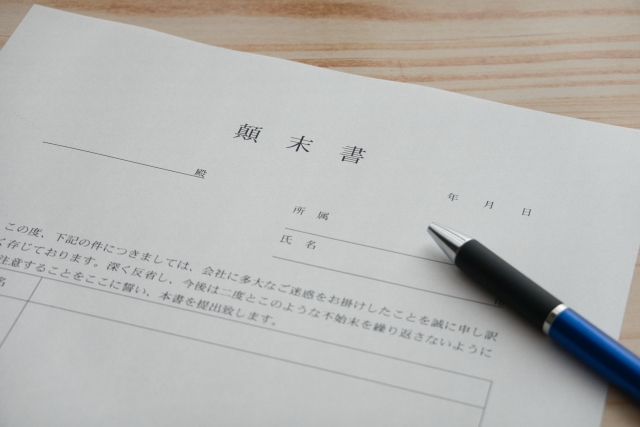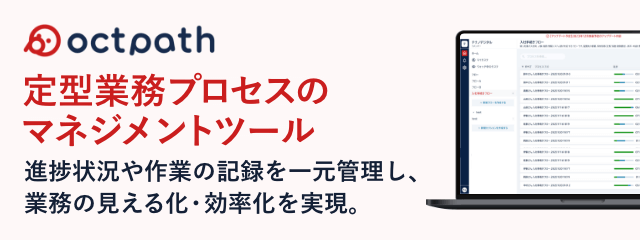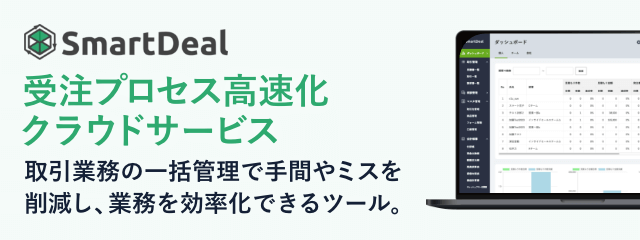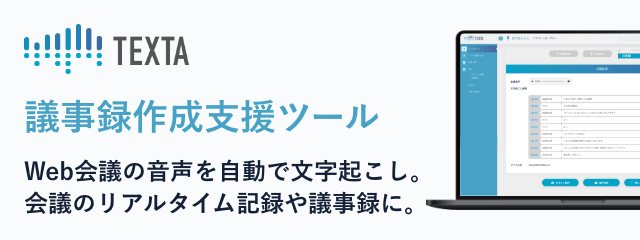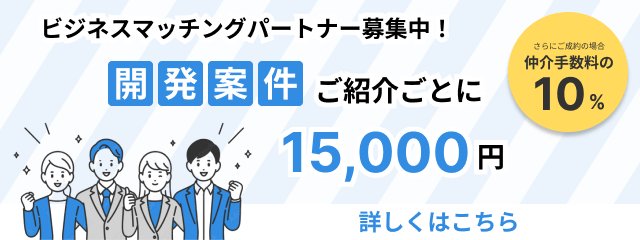2025.04.22
業務の平準化とは?標準化との違い・使い方をわかりやすく解説
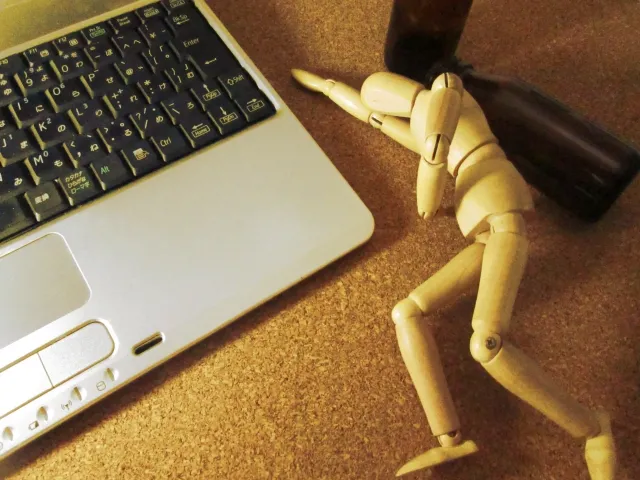
業務の平準化とは、業務量や負荷の偏りをなくし、均等な作業配分を実現することを指します。企業においては、特定の時期に業務が集中することで発生する生産性の低下や、従業員の負担増加が問題視されることがあります。こうした問題を解決するために、平準化の概念が重要になります。
本記事では、業務の平準化について詳しく解説し、標準化との違いやメリット、具体的な方法についてわかりやすく説明します。
目次
平準化とは?

平準化とは、業務や生産活動において作業量の波を抑え、均等に分配することで安定した業務運営を実現する手法のことです。特定の時期や担当者に業務が集中すると、生産性の低下や負担の増大につながります。
平準化を行うことで、業務の効率化やコスト削減が可能になり、持続的な成長が促進されます。
平準化の言葉の使い方・例文
業量を均等に分配し、安定した状態を作ることを意味します。以下のような例文で使われます。
- 業務の平準化を進めることで、繁忙期と閑散期の差を減らし、作業負担を均等にした。
- 製造ラインの平準化を図ることで、生産効率が向上し、納期の安定化につながった。
- サービス業においても、顧客対応の平準化を行うことで、スタッフの負担を軽減できる。
このように、業務の偏りをなくし、スムーズな運営を目指す場面で活用されることが多い言葉です。
平準化と標準化の違い
平準化と標準化は混同されやすいですが、それぞれの目的が異なります。
| 平準化 | 業務の量や負荷の波を均等にし、業務の偏りを減らすこと |
|---|---|
| 標準化 | 作業手順やルールを統一し、業務の進め方を一定にすること |
例えば、ある企業が「毎月の業務量にばらつきがあるため、タスクを分散して平準化を図る」場合、これは平準化の取り組みです。一方で、「業務の進め方を統一し、どの担当者でも同じ手順で対応できるようにする」ことは標準化にあたります。
両者は密接に関係していますが、平準化は業務の負荷を均一にすること、標準化は業務のやり方を統一することが目的であるため、正しく区別して活用することが大切です。
平準化と平準生産性の違い
平準化と平準生産性も似た概念ですが、適用される範囲に違いがあります。
| 平準化 | 業務全体のバランスを調整し、負荷を分散すること |
|---|---|
| 平準生産性 | 生産活動において一定のペースで製品を作り続けること |
平準生産性は、特に製造業において重要視される考え方で、例えば「1日の生産量を均等にし、ムリ・ムダ・ムラを排除する」といった取り組みが該当します。 一方、平準化は生産業務だけでなく、オフィスワークや接客業などさまざまな業種にも適用されます。例えば、カスタマーサポート業務で特定の時間帯に問い合わせが集中しないように、シフトを調整することも平準化の一例です。
このように、平準化は広範な業務のバランス調整を指し、平準生産性は生産プロセスに特化した概念である点が違いとなります。
業務の平準化をするメリット

業務の平準化を実施することで、企業はさまざまなメリットを得られます。
業務負担の偏りをなくすことで、安定した生産性を維持しやすくなります。また、業務の効率化により、残業時間の削減やコスト削減が実現できます。
| 安定した生産性の維持ができる | 業務の負担が特定の時期や特定の人に集中しないため、常に一定の生産性を維持しやすくなります。 |
|---|---|
| コスト削減ができる | 業務の偏りを減らすことで、残業時間の削減や不要なリソースの削減につながり、結果としてコストの最適化が可能になります。 |
| 属人化の解消に繋がる | 特定の人に業務が集中する属人化を防ぐことで、誰でも対応できる体制を整え、業務の継続性を確保できます。 |
業務平準化の方法

ここからは業務平準化の方法をご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
①現状の業務量を把握する
まずは、現状の業務量や担当者ごとの負荷を可視化します。どの業務が、どのタイミングで、どのくらい発生しているのかをデータ化し、偏りの原因を分析します。業務管理ツールやタスク管理システムを活用することで、業務の流れを把握しやすくなります。また、従業員へのヒアリングを行い、実態に即した業務量の測定を行うことも重要です。
②業務の偏りを調整する
業務量の偏りを分析した後は、タスクを適切に分配し、負荷が特定の部署や担当者に集中しないよう調整します。例えば、繁忙期と閑散期を考慮し、タスクを前倒しで処理できるようにしたり、チーム間で業務を共有できる体制を整えたりすることが有効です。また、マニュアルや業務プロセスを見直し、作業効率を向上させる施策を取り入れることも有効です。
③目標を設定する
業務の平準化を進める際には、明確な目標を設定し、成果を測定するためのKPI(重要業績評価指標)を決めることが重要です。例えば、「特定の期間に業務が集中しないようにする」「1人あたりの業務量を均等化する」「残業時間を○%削減する」など、具体的な指標を設定します。これにより、業務平準化の進捗を確認しながら改善を進められます。
④業務平準化を実行する
計画が整ったら、実際に業務の配分を調整し、適切な作業量を維持できる体制を構築します。業務の流れをスムーズにするために、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やシステム導入などのITツールを活用するのも有効です。定期的に状況をチェックし、必要に応じて業務の見直しを行い、柔軟に改善を重ねていくことが求められます。また、従業員の意見を反映しながら、持続可能な業務のバランスを整えることも大切です。
業務平準化には業務改善ツール「octpath」がおすすめです。
平準化に関するよくある質問

最後に、平準化に関するよくある質問をまとめました。
Q.トヨタが取り入れている平準化とは?
トヨタでは「平準化生産(へいじゅんかせいさん)」を導入し、生産量の波を抑えて一定のペースで生産を行うことで、無駄を削減し効率的な生産を実現しています。
Q.平準化のデメリットは?
平準化には、導入に時間と労力がかかることや、柔軟な対応が必要になる点が挙げられます。しかし、長期的には業務の安定化やコスト削減といったメリットが期待できます。
Q.平準化はどのような業界で使われますか?
平準化は、製造業、物流、IT、サービス業などさまざまな業界で使用されます。例えば、製造業では生産計画を平準化して、一定のペースで生産を行うことが重要です。また、IT分野ではデータの正規化や、システムの負荷分散にも用いられます。
Q.平準化の方法にはどんなものがありますか?
平準化を行う方法としては、作業スケジュールの調整やリソースの再配分、需要予測の精度向上、品質管理の強化などがあります。例えば、製造ラインのワークフローを調整して、作業負荷を均等に配分することが一般的な方法です。
Q.平準化の主な目的は何ですか?
平準化の主な目的は、過度な負荷やストレスを回避し、作業効率を向上させることです。これにより、リソースの最適化や不安定な状態の改善が可能になります。例えば、製造業では生産量を均等にし、労働力を効率よく配分することが目標となります。
業務の平準化は企業成長に不可欠!

業務の平準化は、生産性向上やコスト削減、属人化の解消など、多くのメリットをもたらします。特に、業務の負担を均等にすることで、従業員の働きやすさを向上させ、企業全体の成長にもつながります。業務の平準化を意識し、持続可能な業務改善を進めていきましょう。
投稿者
-
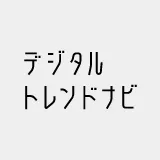
システム開発、Webサイト制作、ECサイトの構築・運用、デジタルトランスフォーメーション(DX)など、デジタルビジネスに関わる多岐の領域において、最新のトレンド情報や実践的なノウハウを発信してまいります。
こんな記事が読まれています
まだデータがありません。